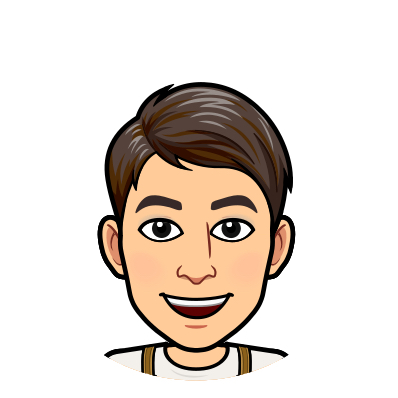11月中旬に、北海道は札幌市郊外の山中にある、パーマカルチャー研究所を訪ねました。
ここでは、代表の三栗さんご家族が自給自足的な暮らしを実現しています。元々この土地は、土建業を営んでいたオーナーが開拓して整備したとのこと。縁あって、ここに住まうようになったそうです。
最も印象的だったことは、ご家族の笑顔と雰囲気が何とも言えない「良い感じ」だったこと。日々の暮らしから充実感を得ていることが雰囲気から伝わってきます。そんな三栗さんご家族も、一時期は大変なご苦労をされたそう。三栗さんご自身もサラリーマン時代はかなりのハードワークで、心身共にボロボロの状態に。
その後、一家でタイのサイナハンを訪ねたことをきっかけに、パーマカルチャー研究所を立ち上げ、現在は「遊暮働学」を柱に個人事業主として活動していらっしゃいます。
ご家族の住まいは、お手製のコンテナハウス。二個のコンテナハウスを繋ぎ合わせて作られています。写真は外部のみですが、お宅の中には生活に必要な設備が一通りそろっています。
東京でも冬はそれなりに寒いのに、北海道でコンテナハウスとは正直驚きました。でも、そこは三栗さんの工夫でカバーしており、窓には中空ポリカ板をはめ込み、壁と床はスタイロフォームで断熱処理を施すなど、寒さ対策が施されています。


そして、山の資源を活かした薪ストーブが室内を丸ごと温めてくれます。コンパクトな住宅ですから、少ない薪で十分に温まるようです。薪が湿っているときや短時間で出かける場合にも備え、灯油ストーブもありました。
水は山の沢から引いており、冬季は凍結防止の為に流しっぱなしにしています。タダで美味しく体に良い水が手に入る環境は最高ですね。
そしてフィールドには、畑と鶏小屋、薪棚、仕事用コンテナハウスが設置されています。
遊暮働学とは

私は20年以上前に、パーマカルチャーという持続可能な農的暮らしに考え方に触れた経緯があります。とてもステキな考え方なのですが、何かひとつしっくりこない部分がありました。一方で三栗さんの提唱する「遊暮働学」はしっくりきます。
遊 ⇒ 遊ぶ
暮 ⇒ 暮らす
働 ⇒ 働く
学 ⇒ 学ぶ
「遊暮働学」は、これらの頭文字をとったものです。読んで字のごとく、暮らしは遊びであり、働くことであり、学びである。暮らすことで人生の全てが満足される。そんなイメージです。暮らすことに中には、食、農、家事、育児など、ありとあらゆる活動が含まれます。
現代の暮らしは細分化され過ぎていて、人間としての全体性が失われている気がします。生きる上での様々な活動を自分達の手に取り戻す、つまり生活の中で手作りする要素を増やし、自分でできることを増やしていく方向性がこれからの社会には必要だと考えています。パーマカルチャー研究所の三栗さんは、そうした在り方を実践している人でした。
私も「遊暮働学」の暮らしを目指して、当ブログ「縄文生活」を充実させていきます。
今度は季節を変えて、訪問したいと思います。今日もご覧いただきありがとうございます。